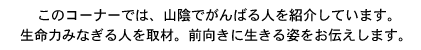|
山陰の輝く人物にインタビュー
|
|
|
 |
|
|
|
連載
|
注目度は全国区へ。『しまね映画祭』企画委員長。
|
(VOL.40) |

【今回の元気人】 毎年数々の名作を選び出す、『しまね映画祭』企画委員長、杉谷さん |
今年で 14 年目となる「しまね映画祭」。毎年、県内各地で多くの映画を上映しているこのイベント。毎年上映される名画、話題作。そして多彩なゲストを呼んでのトークショーなど、斜陽と言われて久しい映画界の一方で、年々地道にファンを増やしている。
その裏で、第一回から携わり、企画委員長として奔走する杉谷さん。「しまね映画祭」に対しての情熱、ご自身の映画感など、熱く語ってくれた 。
しまね映画祭
世界的には“カンヌ”、“ベルリン”、国内を見ても、東京国際映画祭などのメジャーなものから、北海道の夕張、山形、湯布院など、全国100以上の映画祭がある中、「しまね映画祭」も実は大変注目されているという。
「“島根方式”と呼んでいますが、数ある映画際の中でも開催地を固定せず、県内各地で開催しているのは島根だけ。本当の意味で地域密着として、評価されていますよ。はじめは八ヶ所だった開催地も今や二十ヶ所以上。各開催場所のスタッフが、本当に良くやってくれています」と話す杉谷さん。
更に、一昨年からは「映画塾」とも連携して、全国の映画作り希望者が集まる場にもなっている。 「昨年は「白い船」の舞台だった平田でしたが、平田市最後の映像が多く撮れたのも良かった。今年は木次ですが、どんな人達が何をやるのかが、今から楽しみです。」
大人の世界

最近見た作品ではこの二つ。「エレニの旅」(ギリシャ)は、歴史の繰り返しを描いたもの。「春夏秋冬そして春」(韓国)では、人生を季節と照らし合わせた物語。どちらも、画(え)で魅せている。 |
松江で生まれ育った杉谷さん。実家が松江駅近くで旅館をやっていたこともあり、いわゆる“家庭の団欒”のようなものは無かったという。幼稚園の頃からか、一人で近くの映画館に行くようになった。
「最初は訳が分かっていなかったと思いますよ。でも見てた。旅館の常連さんと行くこともあったし、一人で見ていて、家では誘拐騒ぎになっていたこともありました(笑)。だけど、年を重ねるごとに映画の内容が理解できるようになった。幼い頃から見ていたので、一足先に“大人の世界”を見ていたので、ちょっと冷めた子供だったかもしれませんね。」
そんな杉谷さんが大学を出て入ったのが出版業界。当時、高度成長真っ只中の日本。その中でもとりわけ勢いのあった「平凡パンチDX」の編集部に所属することとなった。 「男性ファッション誌の先駆けだったこともあり、銀座、赤坂、六本木など華やかな世界を見せてもらいましたよ。そこには三年間しか在籍しなかったのですが、中身の濃い3年間でしたね」と振り返る。
映画の役割
その後、地元に帰り山陰中央新報を経て、松江テルサに勤務。1992年、「しまね映画際」の企画委員長として会の発足に携わる。
「当時既にあった島根県民会館の「名作劇場」が母体で、それを県内各地に波及させようと言うか、各地の有志が「やろう」と手を挙げてくださったのが「映画祭」に発展しました。」 主に映画の選考、とりわけテーマに即した作品を叩き台に出すのが杉谷さんの役割。

今年も開催する「しまね映画祭」。テーマ作品は、消え行く村を写真に残す親子の物語「村の写真集」。骨髄バンク立ち上げに尽力した神山清子の壮絶な闘いを描いた「火火」の二本。 |
「テーマは一回目から「環境」。今でこそ「環境、かんきょう」と騒いでいるが、当時はそれ程でもなかった。自然環境もあれば、家庭環境もある。裾野が広いんです。そんな中から一つ二つのテーマ、或いは出来事を取り上げ、一つの物語としているのが映画。そこから色々なことを発している。見る側はそれを一つ一つ受け止めなければならない。これは、作り手と見る側との一対一の勝負。特に映画は画(え)で魅せるから、映像を詠み取る力が要るんです。実はこれには体力が必要なんですよ。」
最近の人達、若い人だけでなく五十才以上の人達にも「映像を詠み取る力」が無くなりつつあると感じる杉谷さん。
「私にとって映画とは「自分を映す鏡」です。自分の出来ない体験など、自分が隠している心の奥底などをうまく物語りにしてくれている。現在、松江テルサでも昔の映画を上映してます。そこに来るのは六十代、七十代の方達。その人達がポロポロ涙をこぼしながら昔の映画を見ている。感動もありますが、当時の自分達と照らし合わせ、自分達の清秋時代を映し出しているんです。今の若い人達、子供達に将来同じが同じことができるかと言えば疑問ですね。」
更に杉谷さんはこう続ける。 「限られた空間の中で、“知らない人”とも一つの作品を共有し、そこから発せられるものを同時に受け止める。これは、テレビやビデオ・DVDでは決して出来ない。これが映画なのです。「しまね映画祭」が、映画を見る“動機付け”できればいいと思います。千人の来場者の内、一人でも十人でも多くの人が“映画”という文化を感じ取っていただけたらと思っています。」